田端神社 |
田端神社
応永年間(1394~1427)、品川左京の家臣・良彰がこの地に居住し、京都から北野天満宮の分霊を勧請した。
境内にある四足の木造鳥居は江戸時代のもの、拝殿は改築当時のもので、木造神明造り。
腰痛・足通の神として小槌が奉納されている。境内地から縄文時代中期(約4500年前)の住居跡と多数の縄文土器が出土した。
境内にある四足の木造鳥居は江戸時代のもの、拝殿は改築当時のもので、木造神明造り。
腰痛・足通の神として小槌が奉納されている。境内地から縄文時代中期(約4500年前)の住居跡と多数の縄文土器が出土した。
詳細情報
◆御祭神◆
菅原道真公(すがわらみちざねこう)
天照大御神(あまてらすおほみかみ)
豊受姫命(とようけひめのみこと)
大国主命(おおくにぬしのみこと)
大山祇命(おほやまずみのみこと)
◆由緒◆
応永年間(1394~1427)、品川左京の家臣・良彰がこの地に居住し、京都から北野天満宮の分霊を勧請した。
北野神社(天満宮)と呼ばれていたが後に田の端にあったことから田端天神と呼ばれるようになり、村の名前も田端村と称するようになった。現在の田端の地名はここから来ている。
明治42年(1909)村内の天祖社・稲荷社・子ノ権現社・山神社を合祀。田端神社と改称。
周囲に樹木が多く閑静な佇まいとなっている。
境内にある四足の木造鳥居は江戸時代のもの、拝殿は改築当時のもので、木造神明造り。
腰痛・足通の神として小槌が奉納されている。
境内地から縄文時代中期(約4500年前)の住居跡と多数の縄文土器が出土した。
◆例祭◆
9月13日
◆施設◆
本殿、神楽殿、
◆ご利益◆
合格祈願、所願成就、商売繁盛、金運上昇 他
アクセスマップ
この近くにある物件はこちら!
お知らせINFORMATION
もっと見る
%%REPLACE_WORD_COMPANY%%
%%REPLACE_WORD_TEL%%
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:%%REPLACE_WORD_FREE2%%
定休日:%%REPLACE_WORD_FREE1%%
高円寺駅前店
03-3330-8100
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F

 English avilable
English avilable


 新築一戸建て
新築一戸建て 中古一戸建て
中古一戸建て 中古マンション
中古マンション 土地
土地 条件から検索
条件から検索 学区から探す
学区から探す 町名から探す
町名から探す

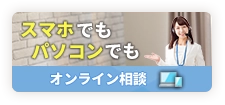
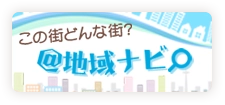

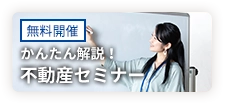
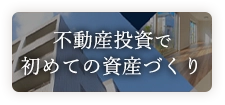
 会社概要
会社概要 スタッフ紹介
スタッフ紹介 代表インタビュー
代表インタビュー